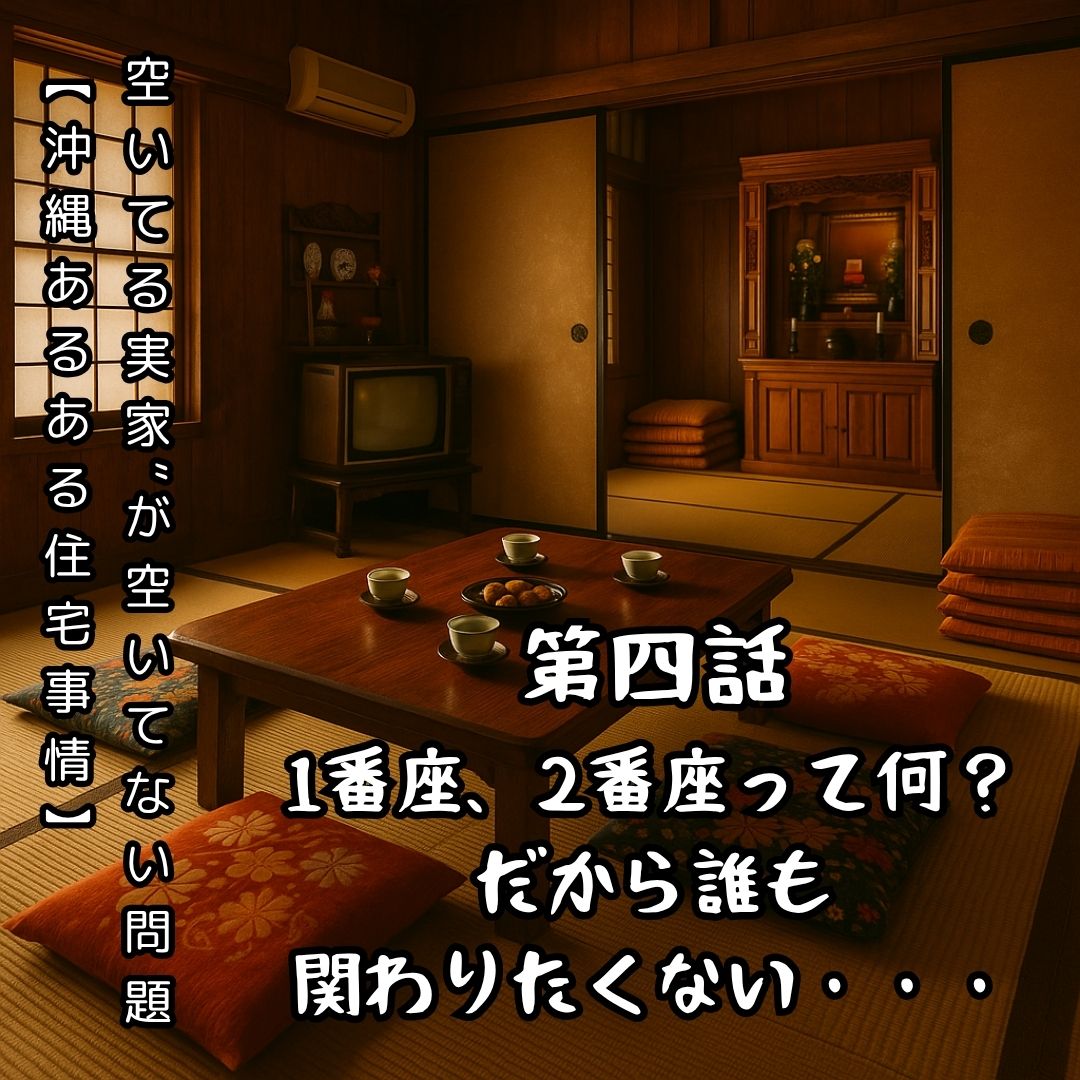そんな疑問を胸に、久しぶりに実家の中へ足を踏み入れると──
すぐに目に入るのが、**“1番座”と“2番座”**の和室。
沖縄の昔ながらの住宅には、洋室やLDKのような区分けではなく、
お客様を通す1番座と、仏壇が鎮座する2番座という“格式”ある空間が存在します。
📍1番座は「お客様専用」、だけど普段は誰も使わない…?
1番座は、床の間があり、親戚が集まる旧盆や正月には
**カメーカメー攻撃が始まる“接待の間”**として活躍する空間。
👩🦰「親戚のオバァが陣取る部屋だから、昼寝なんて絶対ムリ〜」
👨🦱「正月はここで三線と泡盛が回り始めるよな〜」
そんな1番座、普段はほとんど使われることがなく、
でも「荷物を置くのはダメ」「子どもが走り回るのもダメ」という
**“見えないルール”**が未だにしっかり生きているのです。
🛐2番座は「仏壇の間」、神聖すぎて誰も手を出せない
そして、その隣にあるのが2番座。
ここには大きな仏壇が置かれており、家の中でもっとも“神聖な部屋”とされます。
👵「そこはじぃが毎朝ウートートーしてた場所だからね〜」
👴「昔は子どもが入るだけで怒られたさ〜」
エアコンをつけて寝室にしたい?
リフォームで間取りを変えたい?
──そんな話を出しただけで、空気がピリッと張り詰める…。
👵「長男が継ぐって決まってるんだから、勝手に触ったらダメさ〜」
👨🦳「わしも触りたくないよ、ウチナーンチュは仏壇に弱いからよ〜」
💭だから、誰も手を出せない…
🏚「長男が継ぐんでしょ?」
👩🦳「ウチらは二女だから関係ないさ〜」
👨🦳「でも長男、今は関東に家建ててるし…」
👩🦰「“誰が住むか”って、誰も決めてないさ〜」
気づけば、誰も入らず、誰も触らず、ただ時間だけが流れていく。
👵「あの家ね〜、空いてるけど空いてないんだよ…」
👴「オジーが亡くなってから、時が止まったままださ〜」
📌建築士からのアドバイス
「“触れないから触らない”のではなく、“触れるように設える”ことも、住まいの継承です。」
1番座も2番座も、もともとは人を迎え、心をつなぐ場でした。
その役割が終わったからといって、閉じたままにしておくのではなく──
「今の暮らしに合うカタチ」で、もう一度“意味のある空間”に変えていくことも可能です。
まずは「誰が使うか」ではなく、
「どうすれば使えるか」から考えることが、住まいの未来を動かします。
📚次回|第5話に続く!
「誰が住むの?誰が継ぐの?」
──気づいた時には、家も気持ちも置いてけぼり…
沖縄あるある“空き家”の終着点と、
そこからはじまる、未来への一歩をお届けします。