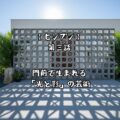沖縄あるある 住宅事情 スケブロ
沖縄の屋根や門柱に必ず鎮座する守り神、シーサー。その独特な姿には、長い歴史と壮大な旅の物語が秘められています。
シーサーのルーツは古代オリエント
👩 オカー: 「シーサーって、ライオンみたいだけど、沖縄にライオンなんていないよねぇ?」
👷 専門家: 「でーじ良い質問です!シーサーの起源は、なんと紀元前の古代エジプトにまで遡るんですよ。」
シーサーの原型は、古代エジプトやメソポタミアで権威や守護の象徴とされたライオン像です。これが、シルクロードを渡る中で少しずつ姿を変え、中国で**「獅子(しし)」**の姿になりました。
その「獅子文化」が、貿易を通じて**琉球王朝時代(13世紀〜15世紀頃)**に沖縄へ伝わったと考えられています。
権威の象徴から、村の守り神へ
当初、シーサーは魔除けというよりも、中国の慣習にならって王府や貴族の権威を示す象徴として、城や寺院に設置されていました。この時代のシーサーは**「宮獅子(みやじし)」**と呼ばれ、石で造られたものが主流でした。
しかし、17世紀になると、ある事件をきっかけにシーサーは庶民の暮らしへと広まります。
首里王府時代の歴史書には、1689年に冨盛村で火災が相次いだ際、風水師のアドバイスにより、村の火難除けとしてシーサーを設置したという記録が残っています。これが成功したことで、シーサーは村落全体を守る**「村落獅子(そんらくしし)」**として沖縄各地に普及していったのです。
まとめ
シーサーは、古代オリエントから中国を経由して沖縄にたどり着き、最初は権威の象徴でした。それが村人の暮らしを守る守り神へと姿を変えたのです。その姿のルーツは、海の向こうのライオンにあったわけですね。
次回・第二話は、「口を開けて笑う」シーサーと「口を閉じた」シーサー、二体の置き方に隠された**「福を招く秘密」**についてお話しします。