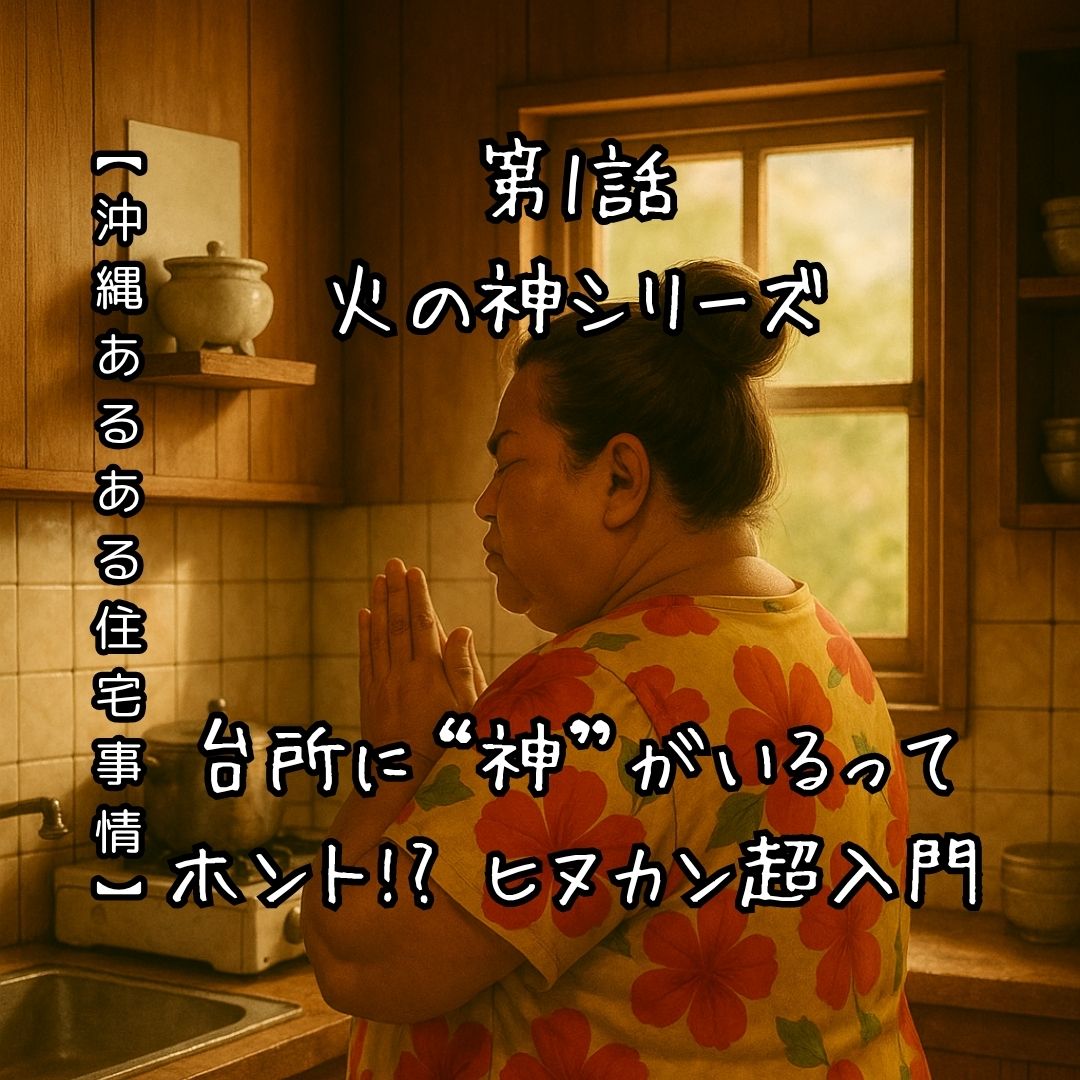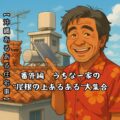🧑🍳実家のキッチンに“謎の灰皿”!?
それ、神様です。
──沖縄の住宅あるある。
古い実家のキッチンに、天井付近の壁にちょこんと置かれた“白い皿のような器”。
中には灰が入ってて、焦げたような跡が──
👩🦰「これ、何かの実験道具?」
👵「バカ言うな!それ**ヒヌカン(火の神)**さ〜」
🔥ヒヌカンとは?
ヒヌカン(火の神)は、台所に祀られる“家庭の守護神”。
沖縄や奄美では、家の中心には「火」があり、
その火を通じて「神さま」とつながるという考え方が根付いていました。
かまど → ガスコンロ → IHへと道具が変わっても、
火の神だけは変わらず“家の中央”に宿る存在として祀られ続けています。
🪔ヒヌカンの基本セット
- 香炉(白い素焼き。足が3本)
- 灰(クチャ=泥灰。洗って乾燥させたもの)
- お供え(炊きたてご飯、ウブク汁、塩水など)
- 火の神の神紙(天井に貼る白紙)
※香炉の足が3本なのは、神様の座る「三本足の神座」を表していると言われています。
👀「なぜキッチンに?」→ 家族を見守るポジション
ヒヌカンは、“家のことを神さまに報告する神様”とも言われます。
毎月1日と15日には、
「家族が無事です」
「こんなことがありました」など、報告と感謝のウートートー(拝み)を捧げます。
🙋♀️ウートートーのやり方(ざっくりVer)
- 線香(1本 or 3本)を灰の中央に立てる
- 手を合わせて、心の中で感謝や報告
- お供えをして静かに祈る
- 線香の灰はそのままでOK、残飯は丁寧に片付ける
🧓設計士泣かせの“ヒヌカン棚問題”
リノベや新築の設計時──
「ヒヌカンの場所も考えてね」と突然言われて、建築士が困ることも。
換気扇の近く?電子レンジの上?
いやいや、目線の高い場所で清浄な位置が基本です!
👷♂️「ヒヌカン棚だけは、施主じゃなく神様優先で配置します…」
💬若者あるある
👦「あれって、神様だったの!?」
👧「香炉の灰、掃除して怒られたことある…」
👩🦰「今は誰も拝んでないけど、捨てるのは怖いね」
👵「使わんでもね、神様は見てるのよ〜」
🏡ヒヌカンがいる家には“火のぬくもり”がある
ヒヌカンを祀るというのは、
「この家を大切に思っています」と火の神に伝えること。
昭和のかまど文化から続く、“台所中心の暮らし”の名残でもあります。
現代のIHキッチンにも、
そっと祀られているヒヌカンが──
今日も静かに、家族の様子を見守っているかもしれません。
✅次回予告|第2話「ヒヌカンの場所が決まらない!? 設計士泣かせの配置バトル」
おばぁ「冷蔵庫の上に置いたら怒られるよ〜」
おじぃ「火の神なのに、火のない家ってどうすんの?」
──次回は、ヒヌカンと現代建築のミスマッチあるある!