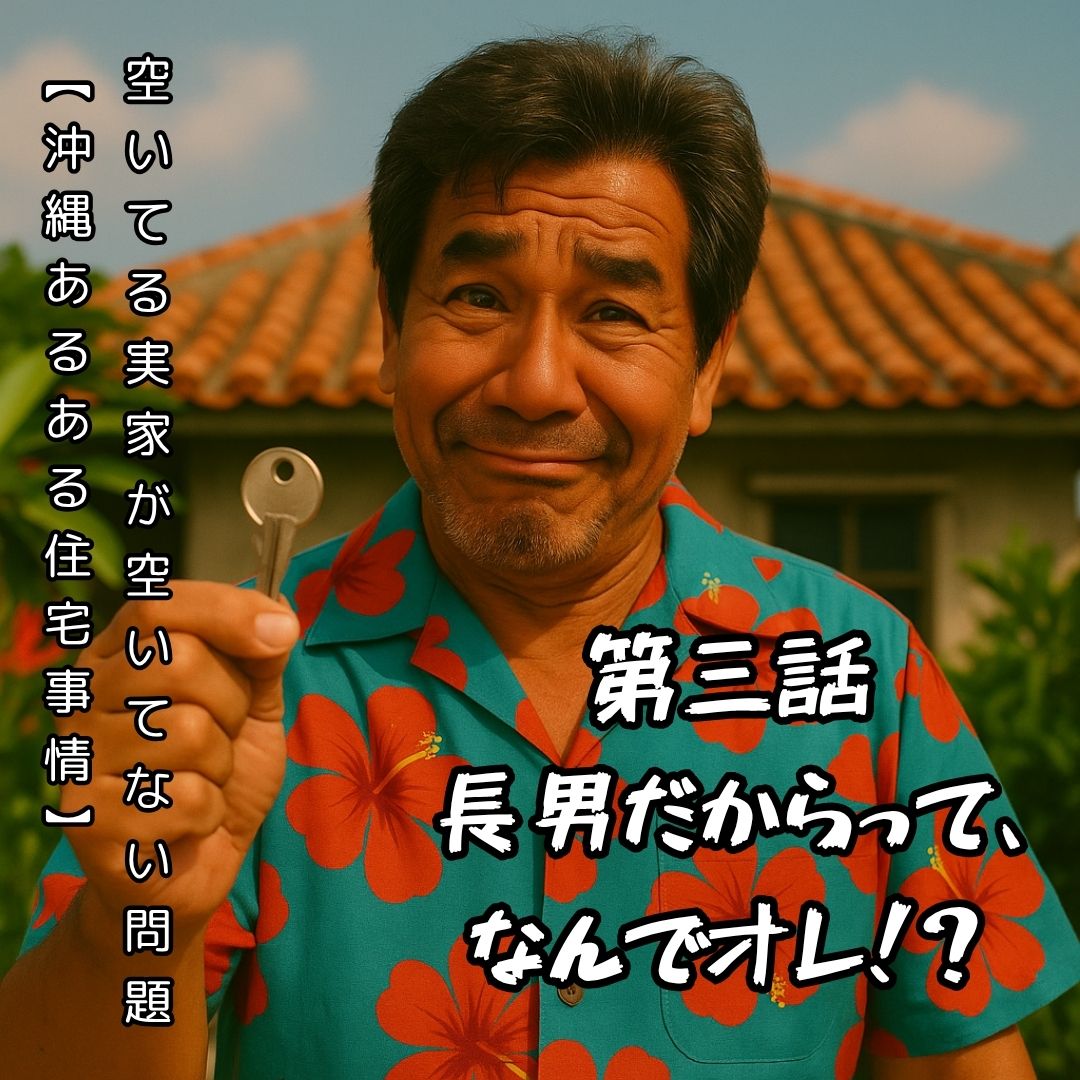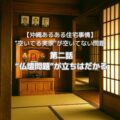〜沖縄あるある“長男ルール”と親戚会議の洗礼〜
👨👩👧👦あの空き家、実は長男名義でした。
「お兄ちゃん、頼むね」
「長男なんだから当然でしょ?」
「うちは“昔から”そうだったさ〜」
親戚から次々と飛んでくる“長男フィルター”。
🏚️鍵を開けたその日から、長男の人生が変わった。
仏壇の世話、法事の調整、名義変更の手続きに草刈り…
一言も引き受けた覚えがないのに、気づけば“空き家管理人”に。
📖沖縄特有の「長男文化」、いまも健在?
沖縄では今もなお、「実家=長男が継ぐもの」という空気感が根強く残っています。
住宅の相続でも、なんとなく“長男が面倒を見る”前提で話が進んでいくことも多く、実際にはそれが原因でトラブルに発展するケースも少なくありません。
📚“あるある”親戚会議の風景
👴「おじぃが建てた家さ〜。大事にせんと」
👩🦰「あんたが長男でしょ?」
👨🦰「オレは県外に家建てたばっかりで…」
→ 話し合いは感情論にすり替わり、
結局は「誰が口を出すか」ではなく、「誰が動くか」で押し切られる。
🧱住宅事情と“仏壇の壁”
長男に押しつけられるのは、空き家だけではありません。
中でも重たくのしかかるのが「仏壇の扱い」。
沖縄では“家=仏壇”という意識も強く、
住宅設計の際も「仏壇スペースありき」でプランを求められることも。
しかも“本家の仏壇”ともなれば…
🗣「この部屋は“1番座”にしないと」
🗣「法事の時に30人は座れるようにしといて」
🗣「クーラーだけはちゃんとつけてよ?」
→ 令和の暮らしに昭和の間取りがねじ込まれる、不思議な設計依頼も多々。
👨🔧建築士の本音
「暮らす人が主役の家づくりにしたい。」
文化は大事。でも、それに縛られて暮らしにくくなるなら本末転倒です。
仏壇も、集会も、“今のライフスタイル”に合わせて見直す時代に来ています。
たとえば──
🛋 1.「1番座・2番座」を“家族が集まるLDK”へリデザイン
「神聖だから使えない部屋」よりも、
「みんなが自然に集まりたくなる場所」に。
たとえば、昔の1番座・2番座をぶち抜いて、約20帖のLDK+仏壇スペースを一角に設ける。
仏壇は壁に埋め込み収納のように設けて、“暮らしに溶け込ませる”という工夫も可能です。
🧘♂️ 2. 法事対応の“スライディング空間”設計
日常はコンパクトな間取りで快適に暮らし、
旧盆や法事のときだけ可動間仕切りで和室を拡張できるように設計。
「ふだんは必要ないけど、年に数回集まる場」として、フレキシブルな空間提案も喜ばれます。
🪑 3. “仏壇ありき”ではなく、“仏壇と暮らす”設計へ
仏壇のために間取りを犠牲にするのではなく、
仏壇と共に過ごせるリビングを提案。
たとえば「仏壇の前にダイニングテーブル」「ソファ越しに仏壇が見える」など、
“拝む部屋”から“つながる存在”として設計に落とし込みます。
🌱 4. 受け継ぐ家=古いままじゃなくていい
昔の建物・しきたり・家族の思い出──全部大事。
でも「引き継ぐ」って、**“残すこと”だけじゃなくて、“更新すること”**でもあります。
今の家族の暮らしにあわせて、住み継ぐ人の“愛着”が育つ空間にアップデートしていく。
それが、本当に“受け継いだ”ってことだと思います。
「長男だから仕方ない」じゃなく、
「長男でも納得できる」実家の形を、設計からつくっていく──
そんな柔軟な選択肢が、これからの沖縄には必要だと感じています。
👵リアルうちなーおばさんのひとこと
👵「あんた長男だからって、全部背負わんでいいさ〜!うまく逃げなさいよ〜」